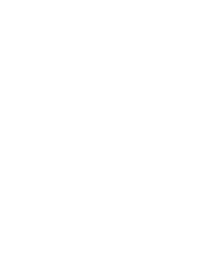世の中が何となくざわつき始めた。今にも
戦争
が起りそうに見える。焼け出された
裸馬
が、夜昼となく、屋敷の
周囲
を
暴
れ
廻
ると、それを夜昼となく
足軽共
が
犇
きながら
追
かけているような心持がする。それでいて家のうちは
森
として静かである。
家には若い母と三つになる子供がいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは、月の出ていない夜中であった。
床
の上で
草鞋
を
穿
いて、黒い
頭巾
を
被
って、勝手口から出て行った。その時母の持っていた
雪洞
の
灯
が暗い
闇
に細長く射して、
生垣
の手前にある古い
檜
を照らした。
父はそれきり帰って来なかった。母は毎日三つになる子供に「御父様は」と聞いている。子供は何とも云わなかった。しばらくしてから「あっち」と答えるようになった。母が「いつ御帰り」と聞いてもやはり「あっち」と答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして「今に御帰り」と云う言葉を何遍となく繰返して教えた。けれども子供は「今に」だけを覚えたのみである。時々は「御父様はどこ」と聞かれて「今に」と答える事もあった。
夜になって、
四隣
が静まると、母は帯を
締
め直して、
鮫鞘
の短刀を帯の間へ差して、子供を細帯で背中へ
背負
って、そっと
潜
りから出て行く。母はいつでも
草履
を穿いていた。子供はこの草履の音を聞きながら母の背中で寝てしまう事もあった。
土塀
の続いている屋敷町を西へ
下
って、だらだら坂を
降
り
尽
くすと、大きな
銀杏
がある。この銀杏を
目標
に右に切れると、一丁ばかり奥に石の鳥居がある。片側は
田圃
で、片側は
熊笹
ばかりの中を鳥居まで来て、それを潜り抜けると、暗い杉の
木立
になる。それから二十間ばかり敷石伝いに突き当ると、古い拝殿の階段の下に出る。
鼠色
に洗い出された
賽銭箱
の上に、大きな鈴の
紐
がぶら下がって昼間見ると、その鈴の
傍
に
八幡宮
と云う額が
懸
っている。八の字が、
鳩
が二羽向いあったような書体にできているのが面白い。そのほかにもいろいろの額がある。たいていは
家中
のものの射抜いた
金的
を、射抜いたものの名前に添えたのが多い。たまには
太刀
を納めたのもある。
鳥居を
潜
ると杉の
梢
でいつでも
梟
が鳴いている。そうして、
冷飯草履
の音がぴちゃぴちゃする。それが拝殿の前でやむと、母はまず鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんで
柏手
を打つ。たいていはこの時梟が急に鳴かなくなる。それから母は一心不乱に夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が
侍
であるから、弓矢の神の
八幡
へ、こうやって是非ない
願
をかけたら、よもや
聴
かれぬ道理はなかろうと
一図
に思いつめている。
子供はよくこの鈴の音で眼を
覚
まして、
四辺
を見ると真暗だものだから、急に背中で泣き出す事がある。その時母は口の内で何か祈りながら、背を振ってあやそうとする。すると
旨
く
泣
きやむ事もある。またますます
烈
しく泣き立てる事もある。いずれにしても母は容易に立たない。
一通
り夫の身の上を祈ってしまうと、今度は細帯を解いて、背中の子を
摺
りおろすように、背中から前へ廻して、両手に
抱
きながら拝殿を
上
って行って、「好い子だから、少しの
間
、待っておいでよ」ときっと自分の頬を子供の頬へ
擦
りつける。そうして細帯を長くして、子供を
縛
っておいて、その片端を拝殿の
欄干
に
括
りつける。それから段々を下りて来て二十間の敷石を往ったり来たり
御百度
を踏む。
拝殿に
括
りつけられた子は、
暗闇
の中で、細帯の
丈
のゆるす限り、広縁の上を
這
い廻っている。そう云う時は母にとって、はなはだ
楽
な夜である。けれども
縛
った子にひいひい泣かれると、母は気が気でない。御百度の足が非常に早くなる。大変息が切れる。仕方のない時は、中途で拝殿へ
上
って来て、いろいろすかしておいて、また御百度を踏み直す事もある。
こう云う風に、幾晩となく母が気を
揉
んで、
夜
の目も寝ずに心配していた父は、とくの昔に
浪士
のために殺されていたのである。
こんな
悲
い話を、夢の中で母から聞いた。