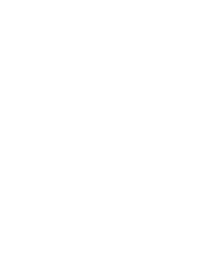六つになる子供を
負
ってる。たしかに自分の子である。ただ不思議な事にはいつの間にか眼が
潰
れて、
青坊主
になっている。自分が御前の眼はいつ潰れたのかいと聞くと、なに昔からさと答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで
大人
である。しかも
対等
だ。
左右は
青田
である。
路
は細い。
鷺
の影が時々
闇
に差す。
「
田圃
へかかったね」と背中で云った。
「どうして解る」と顔を
後
ろへ振り向けるようにして聞いたら、
「だって
鷺
が鳴くじゃないか」と答えた。
すると鷺がはたして二声ほど鳴いた。
自分は我子ながら少し
怖
くなった。こんなものを
背負
っていては、この先どうなるか分らない。どこか
打遣
ゃる所はなかろうかと向うを見ると闇の中に大きな森が見えた。あすこならばと考え出す
途端
に、背中で、
「ふふん」と云う声がした。
「何を笑うんだ」
子供は返事をしなかった。ただ
「
御父
さん、重いかい」と聞いた。
「重かあない」と答えると
「今に重くなるよ」と云った。
自分は黙って森を
目標
にあるいて行った。田の中の路が不規則にうねってなかなか思うように出られない。しばらくすると
二股
になった。自分は
股
の根に立って、ちょっと休んだ。
「石が立ってるはずだがな」と小僧が云った。
なるほど八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には左り
日
ヶ
窪
、右
堀田原
とある。
闇
だのに赤い字が
明
かに見えた。赤い字は
井守
の腹のような色であった。
「左が好いだろう」と小僧が命令した。左を見るとさっきの森が闇の影を、高い空から自分らの頭の上へ
抛
げかけていた。自分はちょっと
躊躇
した。
「遠慮しないでもいい」と小僧がまた云った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中では、よく
盲目
のくせに何でも知ってるなと考えながら一筋道を森へ近づいてくると、背中で、「どうも盲目は不自由でいけないね」と云った。
「だから
負
ってやるからいいじゃないか」
「負ぶって
貰
ってすまないが、どうも人に馬鹿にされていけない。親にまで馬鹿にされるからいけない」
何だか
厭
になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。
「もう少し行くと解る。――ちょうどこんな晩だったな」と背中で
独言
のように云っている。
「何が」と
際
どい声を出して聞いた。
「何がって、知ってるじゃないか」と子供は
嘲
けるように答えた。すると何だか知ってるような気がし出した。けれども
判然
とは分らない。ただこんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けば分るように思える。分っては大変だから、分らないうちに早く捨ててしまって、安心しなくってはならないように思える。自分はますます足を早めた。
雨はさっきから降っている。路はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照して、寸分の事実も
洩
らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうして盲目である。自分はたまらなくなった。
「ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根の処だ」
雨の中で小僧の声は判然聞えた。自分は覚えず留った。いつしか森の中へ
這入
っていた。
一間
ばかり先にある黒いものはたしかに小僧の云う通り杉の木と見えた。
「
御父
さん、その杉の根の処だったね」
「うん、そうだ」と思わず答えてしまった。
「文化五年
辰年
だろう」
なるほど文化五年辰年らしく思われた。
「御前がおれを殺したのは今からちょうど百年前だね」
自分はこの言葉を聞くや否や、今から百年前文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、一人の盲目を殺したと云う自覚が、
忽然
として頭の中に起った。おれは
人殺
であったんだなと始めて気がついた
途端
に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。