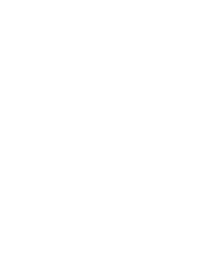腕組をして枕元に
坐
っていると、
仰向
に寝た女が、静かな声でもう死にますと云う。女は長い髪を枕に敷いて、
輪郭
の
柔
らかな
瓜実
顔
をその中に横たえている。真白な頬の底に温かい血の色がほどよく差して、
唇
の色は無論赤い。とうてい死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますと
判然
云った。自分も
確
にこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から
覗
き込むようにして聞いて見た。死にますとも、と云いながら、女はぱっちりと眼を
開
けた。大きな
潤
のある眼で、長い
睫
に包まれた中は、ただ一面に真黒であった。その真黒な
眸
の奥に、自分の姿が
鮮
に浮かんでいる。
自分は
透
き
徹
るほど深く見えるこの黒眼の
色沢
を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで、ねんごろに枕の
傍
へ口を付けて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、とまた聞き返した。すると女は黒い眼を眠そうにみはったまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの、仕方がないわと云った。
じゃ、
私
の顔が見えるかいと
一心
に聞くと、見えるかいって、そら、そこに、写ってるじゃありませんかと、にこりと笑って見せた。自分は黙って、顔を枕から離した。腕組をしながら、どうしても死ぬのかなと思った。
しばらくして、女がまたこう云った。
「死んだら、
埋
めて下さい。大きな真珠貝で穴を掘って。そうして天から落ちて来る星の
破片
を
墓標
に置いて下さい。そうして墓の傍に待っていて下さい。また
逢
いに来ますから」
自分は、いつ逢いに来るかねと聞いた。
「日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう、そうしてまた沈むでしょう。――赤い日が東から西へ、東から西へと落ちて行くうちに、――あなた、待っていられますか」
自分は黙って
首肯
いた。女は静かな調子を一段張り上げて、
「百年待っていて下さい」と思い切った声で云った。
「百年、私の墓の
傍
に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」
自分はただ待っていると答えた。すると、黒い
眸
のなかに
鮮
に見えた自分の姿が、ぼうっと
崩
れて来た。静かな水が動いて写る影を乱したように、流れ出したと思ったら、女の眼がぱちりと閉じた。長い
睫
の間から涙が頬へ垂れた。
――もう死んでいた。